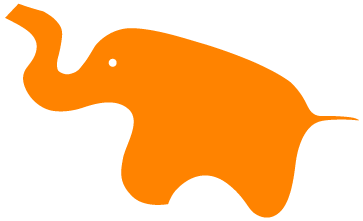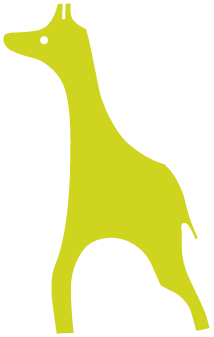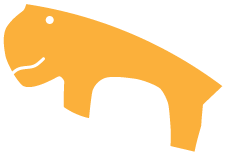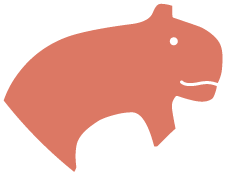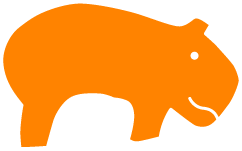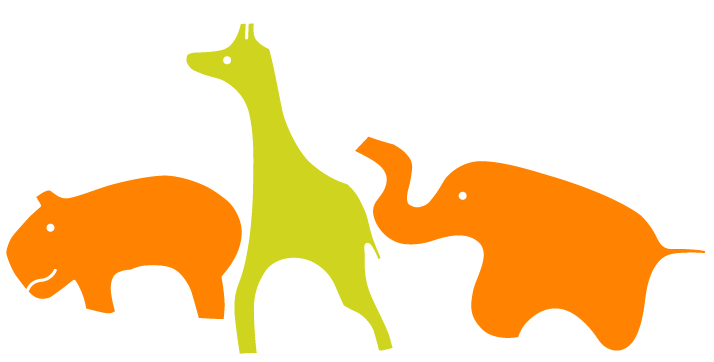
幼児組(3・4・5歳児)の
「とうきょうすくわくプログラム」

![]()
テーマの設定理由
〈テーマに関する子どもの興味関心など〉
子どもたちは、庭や散歩先でダンゴ虫を見つけては、その発見を驚き、喜ぶ姿が連日みられていた。朝も夕方も飽きずにダンゴ虫を捕まえていた子どもたちから「ダンゴ虫、飼いたいな」という声が聞かれた。
活動スケジュール
| 活動内容/日付 | 時間 | 年齢/人数 | |
|---|---|---|---|
| ① | ダンゴ虫の飼育を始めよう | 5月/午前中 | 4・5歳児クラス |
| ② | ダンゴ虫の生態を知ろう | 5月/午前中 | 4・5歳児クラス |
| ③ | ダンゴ虫の絵本を読もう | 6月/午前中 | 4・5歳児クラス |
| ④ | ダンゴ虫のエサの実験をしよう | 6月/午前中 | 4・5歳児クラス |
| ⑤ | ダンゴ虫の脱皮と赤ちゃんの誕生 | 7月/午前中 | 4・5歳児クラス |
| ⑥ | ダンゴ虫との再会 | 12月/午前中 | 5歳児クラス |