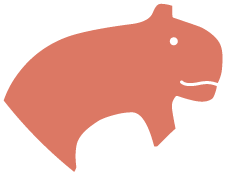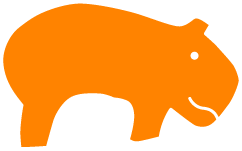![]()
テーマの設定理由
〈テーマに関する子どもの興味関心など〉
・身近な生き物でもある「ちょう」が幼虫から育っていく過程を観察し、生き物の不思議に触れる事で「なぜ?」「なに?」と好奇心を膨らませている子どもたち。
図鑑や道具を利用する事で興味関心をさらに膨らませていく。
活動スケジュール
| 活動内容/日付 | 時間 | 年齢/人数 | |
|---|---|---|---|
| ① | 幼虫を観察しよう | 6月AM・PM | 2歳児/16名 |
| ② | 成長の観察 | 7月AM・PM | 2歳児/16名 |
| ③ | 成長の観察その2 | 8月AM・PM | 2歳児/16名 |
| ④ | 製作と観察 | 9月AM・PM | 2歳児/16名 |
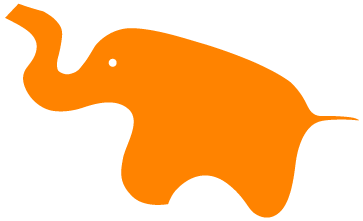
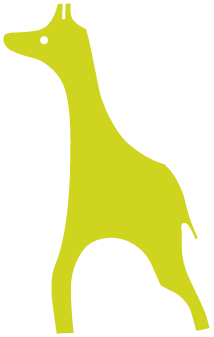
![]()
虫
①幼虫を観察しよう
活動のために準備した素材や道具、環境の設定
幼虫を透明な飼育箱に入れてテーブルに置 き、いつでも見られるようにする。
準備するもの
・虫かご…姿がよく見えるように、大きな透明 な飼育箱で観察を始める
・子どもたちと一緒に調べられるよう、昆虫図鑑を用意する
活動の内容
- 職員の家の庭のみかんの木で生まれた幼虫を観察する
- なんの幼虫か、図鑑で調べてみる
活動中の子どもの姿・声、子ども同士や保育者との関り
「S さんのお家のみかんの木で、あおむしがうまれたよ!」と透明な飼育箱に入れておく。登園してきた子たちが集まってきて、子「え!?アオムシってはらぺこあおむし!?ちょうちょになるの?」 子「なんで黒いの?全然アオムシじゃないじゃん!(黒いとげとげのある幼虫だったため)」 子「もじょもじょ動いてる~!!」と覗き込んでは目を輝かせて思いおもいの言葉を発している。
保「確かに。はらぺこあおむしとちょっと違うよね…ちょっと調べてみるか」と昆虫図鑑を出して子どもたちとめくってみる。いろいろな昆虫に寄り道しながら、アゲハ蝶のページにたどりつく。図解で成長過程が見え、これから緑色になるということもわかった。
子どもたちの姿



振り返り
- 「はらぺこあおむし」の絵本はよく読んでいたので、「あおむし」の言葉にとびつく子どもたちだったが、実際の幼虫(初期)の姿と違いに気が付いたのは2歳児らしく、図鑑で調べることで、次の姿を期待して見守りたい!という子どもたちの様子が印象的だった。
- 黒いトゲトゲから、緑のあおむしに成長すること、みかんの木の葉を食べること、たくさんウンチをすること・・・など観察しながら子どもたちの発見に触れることができた。


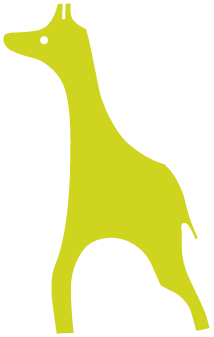
![]()
虫
②成長の観察
〈活動のために準備した素材や道具、環境の設定〉
- いつでも観察できるよう、飼育箱は子どもたちの目、手の届くところに配置する。
- 改めて「はらぺこあおむし」の絵本で興味をふくらませていく
準備するもの
- 虫かご… 姿がよく見えるように透明な飼育箱で観察を始める
- 絵本『はらぺこあおむし』
活動の内容
食事の時以外は、いつでも幼虫の様子を見られるよう、テーブルの上に飼育箱を置き「木から落ちるとちょうちょになれなくなっちゃうから、箱は揺らさないで見ること」と話をしておく。また、お世話についても一緒に考える。
活動中の子どもの姿・声、子ども同士や保育者との関り
- 登園すると「あおむしは?」とどの子も覗きにやってくる。
Aくん「葉っぱがなくなってる!」 B くん「食べたんじゃない??」
A くん「コレはなに?!」保「ウンチだよ~!」子「え~~~!!」
幼虫を持ってきた職員に「あおむしは何食べるの?」と聞いてみると、「みかんの木の葉っぱ」とのこと。庭にもみかんの木があるのを知っている子どもたち。庭遊びの帰りにミカンの葉っぱをもらってかえる。 - 3日ほどで、黒いトゲトゲの幼虫は緑色になり、朝早く登園の子たちは次々と登園する子に「みどりになったよ!」「はらぺこあおむしだ!」と報告している。
活動の様子が分かる写真



振り返り
- 登園時保護者と離れるのを渋る子も「 あおむし さん、一緒に見ようよ」と、声を掛けると 気持ち が 切り替わることもあり、心を動かす出来事の「力」を感じる。
フンの片づけなどは「ウンチ」と聞くと「うぇ~~」という子もいたが、「きれいになったらあおむしも嬉しいよね」と、話ながら子どもたちの前で掃除をしたり、葉を交換したりした。 - 庭で知らない虫を見つけると「調べたい!」という声も出た。図鑑をめくるということのきっかけにもなっており、嬉しい。


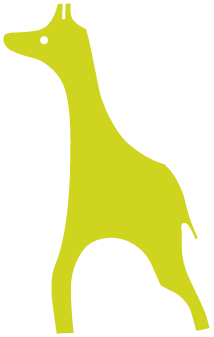
![]()
虫
③成長の観察その2
活動のために準備した素材や道具、環境の設定
- いつでも観察できるよう、飼育箱は子どもたちの目、手の届くところに配置する。さなぎになったら、
静かにしてあげよう。と手には届かない、覗ける場所へ - 羽化を楽しみに、制作へもつなげていく
準備するもの
- 虫かご… 姿がよく見えるように透明な飼育箱で観察を始める
- 絵本『はらぺこあおむし』
活動の内容
- さなぎへと変化、そしてちょうへ。 羽化する様子を観察する
- さなぎになったら、揺らさないよう触らずにみられるところから観察をする。
活動中の子どもの姿・声、子ども同士や保育者との関り
- 毎日かごの中を覗いて見て いる子どもたち。だんだんと動かなくなって、葉っぱの食べが悪くなった。「なんでかなぁ」「元気ないのかなぁ」など子どもたちからも声が出る。「さなぎになるかもよ」と大人から話を聞くと、それを楽しみにしている。箱の床でさなぎになってしまい、対策を調べて「さなぎポケット」を作る
- さなぎからしばらく経ち、朝、 子どもたちとのぞくと羽化している。気づいた子どもたちが箱を囲んで見守っている。片方の羽根が上手く開かず。子どもたちと「飛べるかなぁ」と心配しながら庭のみかんの木に放した。
活動の様子が分かる写真



振り返り
- だんだん動きが少なくなってくるので、全体として観察する時間は少なくなっていくが、興味のある子はそれでもじっと観察している。床でさなぎになり、さなぎポケットに入れて見守ってきたが、最後まで羽根が開かなかった。「飼育」しているために上手く羽根が開かなかったところでは、「命」を保育の中で扱う難しさを感じた。子どもたちには深く聞き取りはせず、それぞれの胸で「どう感じるか」としたが、放した際には「がんばれ~!!」と声をかける子がいたり、「かわいそう」と見ている子がおり、それぞれその子なりに感じるものがあったように見 える。



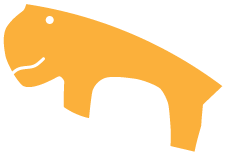
![]()
虫
④製作と観察
活動のために準備した素材や道具、環境の設定
- あおむしからちょうへの変化を楽しむ中で、自分たちで 作って みよう と製作へ誘い掛ける
- 再び飼育
準備するもの
- 虫かご…姿がよく見えるように透明な飼育箱で観察する
- 絵本『はらぺこあおむし』
- 画用紙(台紙と丸く切った色画用紙、チョウの形に切った色画用紙 など)
- 画材
活動の内容
- さなぎになり、ちょうへ の 変化を期待しながら画用紙でちょう を作る 。自分たちでパタパタと飛ばして遊ぶ。
- 絵本「はらぺこあおむし」より、のりを使った制作を楽しむ
- もう一匹、緑になっているあおむしがやってくる。再びちょうになるまでを観察
活動中の子どもの姿・声、子ども同士や保育者との関り
「ちょうちょ作ってみようよ」 と 大人から提案をし、数名の子を誘うと、次々にやってくる子どもたち。
「さなぎもちょうちょになるよね」と 製作を しながらさなぎを観察する子もいる。「あおむしは 葉っぱ が一番好きだよね」と実際の飼育で感じたことも声に出 し、子ども同士での会話も盛り上がりながらの製作 となった。
・2匹目の飼育は、最後の羽化を早い時間の登園の子たち3人でテラスから見送ることができた。
活動の様子が分かる写真



振り返り
- 実際にちょうになる姿を図鑑などで見ながら楽しみにしていた子どもたち。 さなぎから羽化までは時間もかかり、だんだんと気にしない子も出てきた中、 途中で製作 をはさむこと によって、 また興味が沸く子が出てきたことは、保育の効果と感じる。
- 2匹目 のあおむし は、保育者も 今度はちゃんと羽化させてあげたい 。と思いながらの飼育。さなぎになってからは揺らさずに見守るようにした。ちょうど、早く登園した子たちがいる中で 、 しっかり羽化して羽ばたいていく様子が見られた。後から登園した子は「ちょうちょは!?」となっていたが、無事に飛んで行ったことを伝える。その後、庭などでちょうを見つけると「うさぎ組のちょうちょじゃない!?」と出会いを楽しんでいる様子がうかがえた。